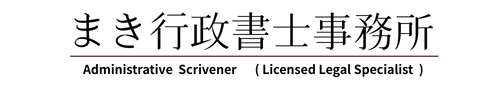公正証書遺言とは
公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)とは、自分1人で作成する自筆証書遺言とは異なり、公証役場の公証人や証人の立ち合いのもと、公正証書として遺言書を作成する方法です。
相続手続きの際の家庭裁判所の検認が不要になったり、公証人が原本の管理を行ってくれたりしますので、より安全な方法といえます。
公正証書遺言には、遺言が無効となってしまう、発見されないなどのリスクを避けられるといったメリットもあります。
公正証書遺言 作成の流れ
- 遺言書の内容を決める
- 誰に何を残したいのか、決めておきます。
具体的には、財産目録のような形で財産を一覧表にしておくと良いでしょう。
相続税がかかる場合には、税理士に事前に相談する場合もあります。
- 必要書類の準備
- 相続人は誰になるのかを調べるために、戸籍謄本などを取る必要があります。
また、遺言書の内容などについて必要になる書類が異なります。
・不動産が相続財産に含まれる場合は、固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書など。
・遺贈がある場合には、遺贈者の住民票など
公証人によっても必要書類が異なる場合もあります。
- 公証人と遺言書作成の日時を決める
- 公証人、証人となる人のスケジュールを確認し、遺言書作成の日時を決めます。
公証役場は日本に約300箇所ありますが、場所に決まりはありません。
また、公証役場に出向くことが難しい場合、「日当」「交通費」を払えば、公証人が自宅や病院に出向くことも可能です。
- 公証役場で公正証書遺言を作成する
- 遺言書作成当日、公証人は遺言内容が遺言者の真意であることを確認し、あらかじめ準備していた公正証書遺言の内容を読み上げます。
遺言の内容に誤りがあれば、その場で修正することもあります。
遺言の内容に誤りがなければ、遺言者と証人2人は、公正証書遺言の原本に署名・捺印をします。
公証人も公正証書遺言の原本に署名し職印を押捺すれば、公正証書遺言の完成です。
- 遺言書を受け取り、公証人に手数料を支払う
- 遺言書は「原本」「正本」「謄本」の3つを作成します。
公証人、遺言者、証人が署名捺印するのは「原本」のみです。
「原本」は公証役場で保存し、「正本」と「謄本」は遺言者に渡されます。
公証人に支払う手数料は、「公証人手数料」(令和6年政令第353号)という政令により定められています。相続人の人数、相続財産、遺言書の枚数などにより決まります。